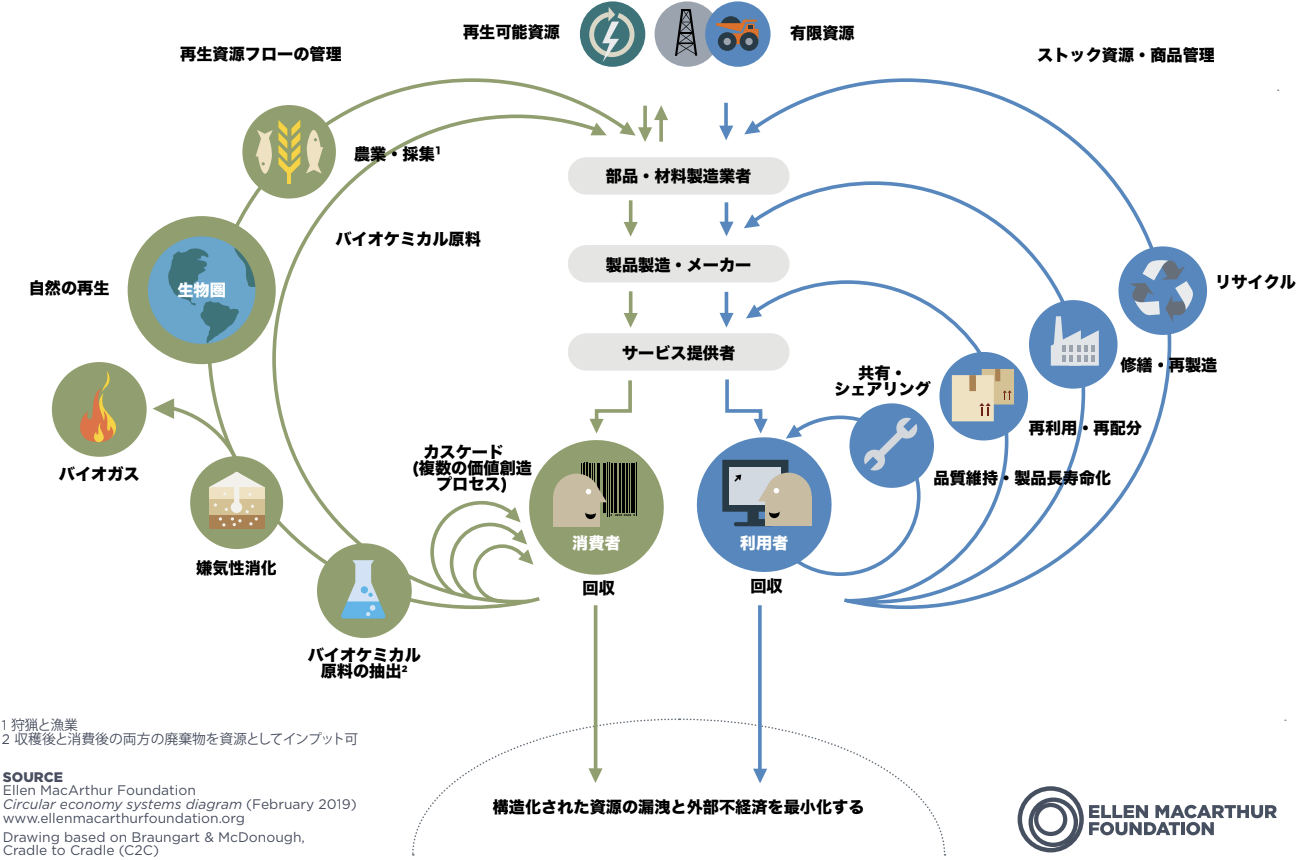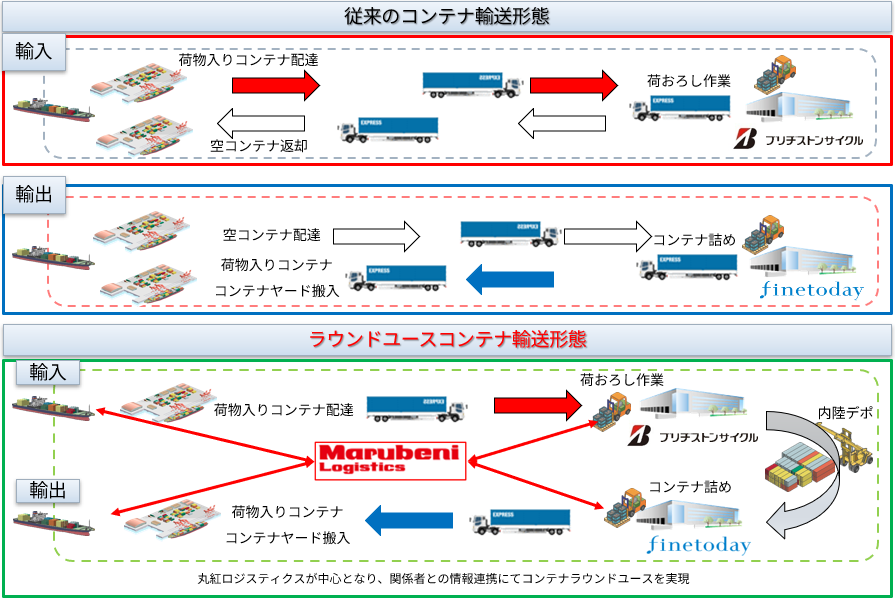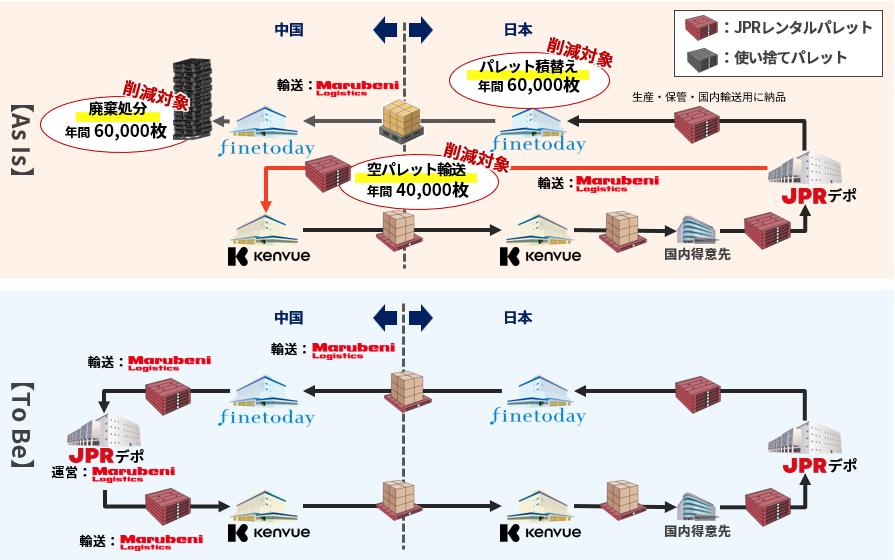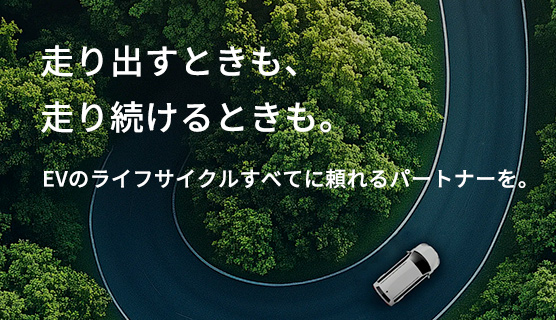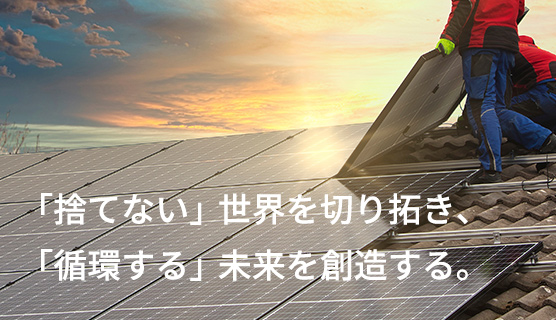丸紅は、米国カリフォルニア州にて使用済み車載蓄電池を用いた系統向け蓄電池※3の事業開発を行うB2U Storage Solutions, Inc.(B2U社)へ出資しています。
B2U社は、電気自動車で使用した蓄電池を効率的に定置型へ二次利用するコンテナ型蓄電池の開発を行い、系統安定化向けの蓄電サービスを提供しています。B2U社の独自開発技術により、使用済み車載蓄電池を解体・再検査・再梱包することなく、定置型として安価で容易な二次利用が可能になります。
世界中のEV普及に伴い、急増する使用済み車載蓄電池の適切な再利用とリサイクル処理による資源の有効活用は大きな社会課題となっています。また、カリフォルニア州は世界で最も再エネ電源導入が先行する地域の一つであり、太陽光発電設備の大量導入によって、日照時間は供給電力に余剰が発生し、夜間は不足する、電力需給バランスの昼夜間差が拡大しています。
出力が不安定な再エネ電源の増加による系統負担増を緩和するため、丸紅とB2U社は、使用済み車載蓄電池を用いて電力需給を調整し、蓄電池の稼働を最適化するデジタルツール開発を通じて、より付加価値の高い調整機能を提供することを目指します。
丸紅は、B2U社への出資を通じて、カリフォルニア州における再エネ目標※4の達成、および電力の安定供給に寄与し、2021年3月に公表した『気候変動長期ビジョン』に掲げる「事業を通じた低炭素・脱炭素化への貢献」を実現するとともに、循環型社会に貢献していきます。